さて、今回からのLesson6では、少し視点を変えて歴史的人物と和菓子の物語を学んでいきます。
今回のページでは文筆家の書物に登場する和菓子について触れながら、その歴史や物語を解説します。
昔から日本の人々の暮らしの一部にあった和菓子。
さまざまな場面で書物にも登場してきますので、しっかりと学びを深めていきましょう。
清少納言と和菓子

古代から中世に使われた甘味料に『甘葛(甘葛煎)』があります。
糖度が上がる冬のツタの樹液を煮詰めて作ったものとされ、砂糖が伝わり使われるようになるまでの間は、甘葛煎が主に使われてたようです。
この甘葛煎が登場する有名な文献に、清少納言が書いた『枕草子』があります。
『あてなるもの』に、削り氷に甘葛煎をかけて食べたことが記されているのです。
現代でいう、かき氷のシロップのようですね。
枕草子には、他にも和菓子が登場します。
『三条の宮におはしますころ』に、清少納言が中宮定子へ、『青ざし』を贈ったという記載が見られるのです。
この青ざしとは、どんなものでしょうか。
青ざしとは、青麦を炒って臼で引き、糸状によった菓子といわれています。
宮中が端午の節句の準備で賑わう中、硯の蓋の上に美しい青い薄紙を敷き、青ざしをのせて
差し上げたという、清少納言の細やかな気遣いが感じられるエピソードと共に描かれています。
清少納言の溢れる文才が感じられる、和菓子の話はまだあります。
貴族の藤原行成から、使いの者を通じて『餅餤(へいだん)』が梅の花と共に贈られたというお話です。
餅餤とは唐菓子の一つで、ガチョウや鴨の子、雑菜などを煮込んだものを餅で挟んだものとされています。
これを、本人が直接持ってこなかったことに、清少納言は「自分自身が持ってこないのはひどく冷淡に思いますが…」とお返事を書きました。
この「餅餤」と「冷淡」をかけた言葉遊びのような機知のある文章に、藤原行成はとても感心したそうです。
華やかな宮中での生活だけでなく、当時の和菓子にまつわる話についても垣間見ることができる枕草子。
和菓子の視点から読んでみると、また一味違う文学の楽しみ方になりそうですね。
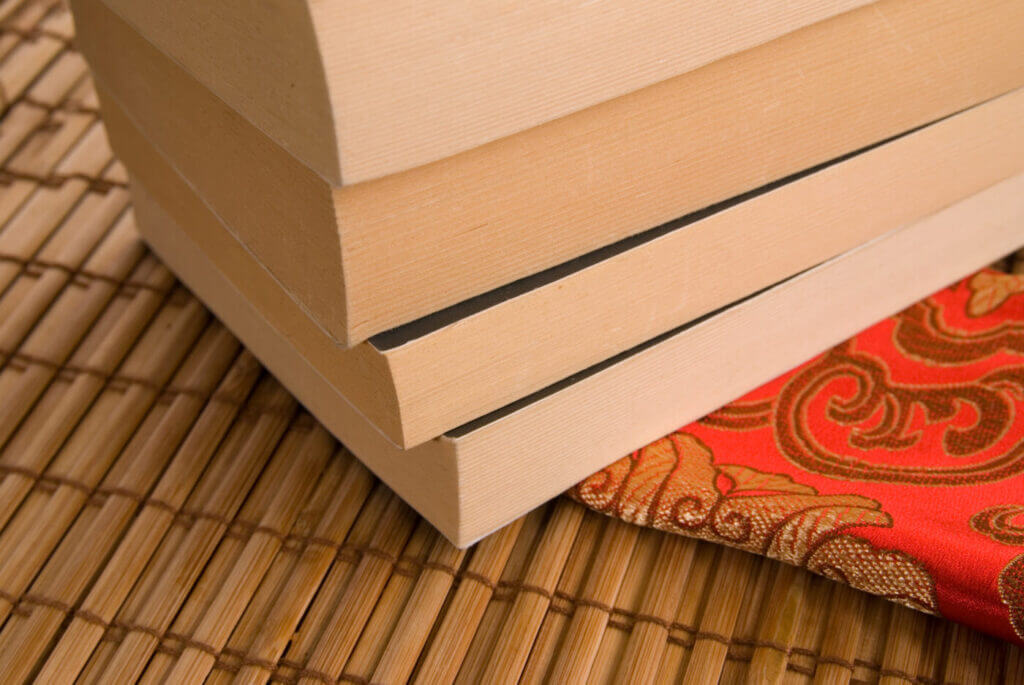
娘が伝える、森鴎外と和菓子
明治の文豪、森鴎外は変わった味覚の持ち主だったようです。
娘たちが記した鴎外に関する記録には、『饅頭茶漬け』なるものが登場します。
これは、葬式饅頭を4つに割り、ご飯の上に乗せ、煎茶をかけて食べたというものです。
子供たちも、父・鴎外を真似て饅頭茶漬けを食べたようですが、それぞれに好みが分かれ、賛否両論あったことが、娘たちが残した文献から伺えます。
また、別のエピソードでは、醬油に浸した焼き餅をご飯にのせ、お茶をかけて食べたことも紹介されています。
鷗外は、珍しい組み合わせのお茶漬けが好きだったのかもしれません。

そのような様子を伝えた鴎外の長女・森茉莉も、文壇で活躍しました。
エッセイの中には、幼い頃の記憶も書かれており、父が宮中からもらってきた菓子についても触れています。
練切など、多くの美しい半生菓子などを見ていた中でも特に、
色鮮やかな有平糖の花菓子がお気に入りだったようです。
有平糖は、ポルトガルから伝わった南蛮菓子の一つです。
リボンのように結ばれたものや波型のものなど、色や形が様々あり、江戸時代後期には贈答品としても好まれていました。
乙女心をくすぐる、幼い頃の楽しかった思い出を思い出させてくれる一品だったのでしょう。
最後に、鴎外の妹・小金井貴美子が記した、兄を思いやる心温まるエピソードがあります。
当時、東京帝国大学(現在の東京大学)を卒業し、留学を希望していてもなかなか叶わず不安な日々を送っていたと思われる鴎外と、貴美子は散歩に出かけました。
当時住んでいた東京・千住からしばらく歩いた先で、休憩の為に掛茶屋に入ります。
そこでくず餅を頼みましたが、少し食べただけで、残りは家族へのお土産として持ち帰ったそうです。
その日の夕食後の団欒の時、家族でくず餅を囲んでいると、思わぬところから会話が弾み、とても楽しいひと時を過ごした鴎外一家。
会話の中で、暗かった鴎外の顔に少し明るさが戻ったことを見逃さなかった貴美子は、
一時でも心をほぐしてくれるきっかけを作ってくれたくず餅をお土産として持ち帰ったことを、
とても嬉しく思ったそうです。
兄を思う妹の優しさが感じられるお話ですね。
